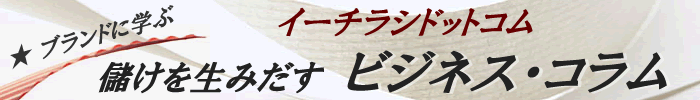古来より日本は大陸(中国・朝鮮)との交流によって、多くの文化を育んできた。
とくに538年の仏教の伝来以後は、百済より医・易・暦などが伝来、経論・律師・禅氏・仏工・寺工なども渡来して、交流も活発になり飛鳥文化の礎となっていった。
578年、聖徳太子の命を受けて、百済から三人の優れた工匠が招かれた。その一人である金剛重光が、大阪・四天王寺を建立した日本最古の企業、金剛組の初代であった。
804年には遣唐使として弘法大師(空海)が中国に渡り、806年に帰国するときには炭焼き技術を持ち帰り、真言宗の布教と共に炭焼き技術を全国に広めた。金剛峯寺を創建した高野山からほど近い紀州南部地方は「紀州備長炭」の産地として有名である。
時が経ち、豊臣秀吉が出兵した文禄の役(1592年)、慶長の役(1597年)では出征した諸藩の多くが、撤兵する際に農民や陶工たちを伴い、農耕技術や陶芸技術を持ち帰った。
肥前国(佐賀県)鍋島藩の藩主・鍋島直茂が連れ帰った陶工のなかに、「有田焼」の祖といわれる李参平(イ・サンピョン)がいた。のちに有田焼はドイツに渡り、ザクセン王・オーガスタ一世の目にとまり、ヨーロッパの名陶マイセンに大きな影響を与えた。
日本人の、心の味である饅頭の起源には諸説あるが、南北朝時代の1349年に中国大陸から渡ってきた一人の禅僧が、点心の饅頭(まんとう)を日本向けに工夫して考案したのが始まりと云われ、今日では最も有力な説となっている。
京都・建仁寺の禅師「龍山」が、宋での修行を終えて帰国する際に、俗弟子の一人だった中国人「林淨因」を連れてきた。淨因は奈良に暮らしの居を構え、饅頭を作って売り出した。これが、日本の伝統的な味となる「おまんじゅう」の歴史の始まりと云われる。
当時、寺院は宗教学問の場だけでなく、上流階級の社交の場としても使われていた。この頃の日本の茶菓子は、胡桃や栗などの木の実、干し柿などといったものだった。淨因の作る饅頭(まんとう)は、母国・中国では豚肉や野菜を詰めていたが、肉食が許されない僧侶たちのために、小豆を煮詰めて甘葛の甘味と塩味を加えて餡を作り、これを皮に包んで蒸し上げたもので、その画期的な甘味は寺院に集う上流階級の人たちに大評判となった。
その後、饅頭は子孫たちに受け継がれ、奈良・林家と京都・林家に分かれて営業した。1467年に応仁の乱が起こり、京都は焼け野原となってしまった。戦乱を避けて京都を離れた林家は、三河国(愛知県)設楽群塩瀬村に住み、城主の娘を嫁に迎えた。このことが古文書にも残されていることから、林家は城主と婚姻関係を結べるほどの身分であったことが窺える。塩瀬村で作る饅頭も評判を呼び、「塩瀬」が饅頭の代名詞にもなった。林家の姓を「塩瀬家」に改め、ここが「塩瀬総本家」のルーツとなる。
戦国時代中頃の1489年に、政争と人事に疲れ果てた室町幕府八代将軍・足利義政が京都郊外の東山に、銀閣寺を建立した。銀閣寺に蟄居した義政は、地味だが奥行きの深い趣味として茶道と出会った。茶道は当時の一部粋人たちの間にも、趣味・道楽として楽しまれていた。やがて義政の凝りように促され、広く世間に普及するようになっていった。
この頃の茶道は単に茶を点てるだけでなく、茶室の設計や内装、掛け軸や生け花、菓子や料理、踊りなどの接客の余興まで、茶を楽しむための総てが演出された。
このような世相は、のちに東山文化と呼ばれるようになった。織田信長が足利義昭を京都から追い出し、室町幕府が滅ぼされ、安土桃山時代になってからも、この文化は継承された。信長や秀吉は戦場においても茶室を造り楽しんだとされる。
この頃には茶器にも趣向が凝らされるようになり、千利休などが粋人たちの寵愛を集めるようになり、元禄時代になると一般庶民にまで広まるようになった。茶道はお茶受けに食される和菓子にも大きな影響を与え、菓子文化も共に発展した。東山文化が栄え始めた頃、再び京都に戻った塩瀬は大繁盛となり、塩瀬があった烏丸三条通り下ルの辺りは当時、饅頭屋町と呼ばれるほどになった。義政からは「日本 第一番 本饅頭所 林氏 塩瀬」の看板を授かる。時の帝である後土御門天皇からは「五七の桐」の家紋を拝領するようになった。
こうした時代のなかで塩瀬の饅頭は、織田信長、明智光秀、豊臣秀吉、徳川家康などの、時の権力者に愛好されていた。京都での繁盛が続くなか、関ヶ原の戦いを制した家康が、
1603年に江戸開城したと時を同じくして、江戸にでて商売を始めるようになった。
塩瀬と家康の関係は、1575年の長篠の合戦にて、七代目林宗二が陣中見舞いとして「大饅頭」を献上した頃から始まった。家康は兜に盛って神社に供え、戦勝を祈願したことから「兜饅頭」とも呼ばれた。1615年の大阪夏の陣では敵将・真田幸村に攻め立てられて、一命を落とす瀬戸際があった。そのときにわずかな手勢を引き連れて逃げ込んだ所が、林淨因が居を構えていた林神社だった。家康は勝利後、塩瀬家に鎧一振りを贈ったと云われる。
1611年に即位した後水尾天皇の以後は、皇室との関わりもより深くなり、明治初年からは宮内省御用達を務める。第二次大戦では戦死者への下賜菓子も塩瀬で造られた。このような歴史を刻んできた塩瀬の饅頭は、上流階級にのみ許された超高級菓子だった。
今でこそ有名デパートへ足を運べば、誰もが買うことが出来るようになったが、それはごく最近のことである。現会長の川島英子氏(34代店主)の、父上(32代)が店主だった戦前までは、宮内庁や宮家、軍隊や官庁などからの注文販売が主であった。母上(33代)が店主の時には、法事や結婚式の引き出物としての注文を受けるようになったが、一般的な小売りはほとんど行っていなかった。
英子氏が社長を継いで間もなくの頃、銀座・松屋からリニューアルを機に、出店のオファーがあった。頑固な先々代が常日頃「店ざらしでお菓子は売らない」「饅頭は蒸したてを食べてもらいたい」と、デパートの出店を断り続けていた。英子氏は「売り場に饅頭を蒸すブースを設けてくれるなら」との条件付きで出店することになった。しかし、20年でやっと一人前と云われる塩瀬の職人が、出店のために拘束されることになる。伝統ある塩瀬の味を守りつつ、新たな挑戦をするには大きな賭となった。
「時代に即した新しいこともしなければ、暖簾は続かない。日本の和菓子は外国にない独特のもの。技術を伝承しなければならない責務がある。新しい商品は思いつきや、その場凌ぎでは絶対にダメ。私たちは技術を通して、お客様へ心を伝えているから」
塩瀬の饅頭は、これまで上流階級の嗜好品として支持されてきた歴史がある。それは、商品を生み出す総てへのこだわりと、しっかりとした本物の味が、支持の証となっている。
そして、これを守ろうとする心意気が、650年以上もの長きにわたり、暖簾をつなぐことができたのであろう。
塩瀬総本家・本店奥に「淨心庵」と名付けられた茶室がある。「菓子を求めてきたお客様に、ちょっと腰を掛けてゆっくりしてもらえる空間」を提供したかったという。もしかしたら、老舗の味の凄さとは、食した時に感じる「心豊かなひととき」にあるのかも知れない。
|